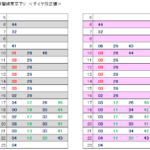
上野東京ラインについて考える~2017年10月14日ダイヤ改正
写真. 2017年10月ダイヤ改正で増加する品川発着の特急列車 ※この記事は2017年7月に発表されたプレスリリースを読み取り、発車時刻は推定したものです。実際の時刻表をベースに詳細な解析も実施しています。それに関しては以下のリンクからご覧ください。 2017年10月に常磐線関連...
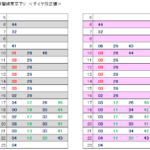
写真. 2017年10月ダイヤ改正で増加する品川発着の特急列車 ※この記事は2017年7月に発表されたプレスリリースを読み取り、発車時刻は推定したものです。実際の時刻表をベースに詳細な解析も実施しています。それに関しては以下のリンクからご覧ください。 2017年10月に常磐線関連...

多くの人にとってなぞの存在、お座敷列車。ここでは、お座敷列車の探しかた、予約から実際の乗車まで2015年6月の乗車体験を例に示します。また、お座敷列車特有の車内についてもまとめます。
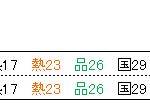
2017年3月4日にダイヤ改正が実施されました。JRからの案内では一部列車の15両化のみでしたが、実際はどうなのでしょう?両数は時刻表からは確認できませんので、運転時刻のみの記載とさせていただきます。 ※この記事は2017年10月ダイヤ改正前に書かれたものです。2017年10月ダイヤ改正でのダイヤ...

東武鉄道がダイヤ改正するという情報がありました(新鮮味がないですね)。そこで、私なりに考えてみます。 写真. 東武鉄道ご自慢のリバティ 特急の増発、会津田島までの延長 今回の1番のポイントは、新型特急による会津田島までの直通でしょう。 図1. 東武特急の運行イメー...

写真1. 接続する様子(上りホーム) 京成線のジャンクションである青砥。ここより都心側では京成上野方面と日本橋方面(都営線直通)に分岐します。この両者へのアクセスを確保することが重要です。そのアクセスはどのように確保しているのでしょうか。時刻表での確認と現場での調査の両方から考察しました。...

写真1. 下りの田園都市線準急と大井町線急行が到着 接続風景とは 異なる路線だけれども、関係が深い2路線。これらの路線の結節点ではどのような接続が行われているのか(あるいは直通しているのか)、それを探るシリーズが「接続風景」です。この2路線、そしてジャンクションの選定は私が実施いたします...

東急東横線と目黒線。これらは別系統として知られていますが、実はダイヤ上は連携を取っています。そして上り限定ですが、目黒線各駅停車の驚くべき活用方法を紹介します。

相鉄の都心直通プロジェクト実現が延期されるようですね。ここで、相鉄直結の概要を振り返るとともに、「都心」のどこに直結するのか考えてみます。